「〈ミリオンカ〉の女 うらじおすとく花暦」 高城高
1892年、ロシア帝国。極東の玄関口であり、ロシア人以外に清国、朝鮮、そして日本人など多様な国籍を持つ人種が入り乱れる国際色豊かな港町ウラジオストクに一隻の日本船が入港した。その船にはひとりの女性の姿があった。ウラジオストクに商会を構えるアメリカ人グレゴーリィ・ペドロフの義娘、エリサヴェータ・ギン・ペドロヴァ。彼女は数奇な人生を歩んだ女性だった。
函館の大火災によって両親と生き別れた彼女はペドロフの部下で船乗りの中田由松に拾われてペドロフの庇護を受けるもその後、ウラジオストクで洗濯屋を営む日本人夫婦に養子に出される。しかし、洗濯屋夫婦はその裏で貸座敷と呼ばれる日本式の妓楼・日之出楼の下働きとして彼女をこき使い、やがて娼妓として客を取らせるようになる。屈強なロシア男にも負けない床あしらいを身につけた彼女はやがて浦潮吟としてその名を多国籍な男たちの中で知られるようになっていく。16歳から20歳までを娼妓として過ごしたお吟だったが、やがてその事実がペドロフの知るところとなると力づくで日ノ出楼より奪還される。そしてペドロフの正式な娘となった彼女は函館へと行き、そこで現地の水上警察の加納警部たちの手によって彼女の真の両親の死の真実と自身の本当の名を知ることとなった。しかし、彼女は本当の名を函館に置いてくることを決めるとロシア人・ギンとしてウラジオストクに戻っていったのであった…。
というのが本作の前日譚である「ウラジオストクから来た女ーー函館水上警察」の中で描かれた彼女の人生である。そして、本作はそのスピンオフとしてお吟がウラジオストクに戻ってからの彼女の姿を描いている。
まずお吟が函館と似ていると語るウラジオストクの精密な描写に呑まれる。私はあまりイメージがなかったが日露戦争以前の極東の各都市には日本人が多く移住しており、現地でアグレッシブに日本人社会を形成していたことに驚かされる。日本人移住の尖兵となっていた日本の妓楼とその経営者、そこで現地の中国人に身請けされた仕切られ女たちの強かさ。そして港では清国のマンザと呼ばれる苦力たちよりも洗練された荷受の技術とその腕力を誇っていた日本の沖仲仕たち。そして、ロシアの社交界や財政界、元同業者の仕切られ女たちにも抜群の知名度とともに顔の効くお吟の洗練された文化を持つ華やかなロシア人社会とミリオンカと呼ばれる地区の猥雑な中国人社会の両方を軽やかに行き来する政治力と行動力も読んでいて小気味がよい。
またサブタイトルにある通り、全編を通してお吟の目を通して語られる花の描写がウラジオストクの季節の移り変わりをよく写していて、まさにウラジオストクの花暦となっている。
ただ、一風変わったロシアのお嬢さんが社交界で快活に生きていく物語なのかというとそうでもなく、その手触りは暗黒社会のハードボイルド小説そのものであるから脱帽である。朝鮮人参を狙う山賊を青龍刀で退治する話や、腐敗したロシアの公権力の話、狡猾な妓楼の主の暗躍を阻止したり、港の縄張り争いについて各国の労働者組合の代表による会合が催されたり、反目する名門一族の間で悲恋があったり、家同士がお互いの名誉を賭けて決闘をしたり、とその多彩さと面白さには目を剥くものがある。
お吟以外の登場人物も魅力的だ。お吟の付き人の由松は小柄な日本人ながら英語が堪能で商会の表の業務の他に仕込み杖片手に荒事にも飛び出していくナイスダンディだし、ミリオンカの老板の仕切られ女で強かな麗花姐さん、お吟を身請けしようとした縁で今でも彼女によくしてくれる沖仲仕の頭の安中組の清吉親分、商会の主人ながら若いときの血が抑えられずに鯨漁に血道をあげるお吟の父グレゴーリィ。前作の主人公・加納警部も顔を出すからサービス満点だ。
日本人にあまり馴染みがあるとは言えないウラジオストクという国際都市の姿を描いた歴史小説でありながら、極上のハードボイルド小説で抜群の読み応えがある大作だった。面白かった、おススメです!

書影。寿老社という聞き馴染みがない出版社の作品だが、北海道の出版社らしくアイヌの書籍などを刊行してるみたい。
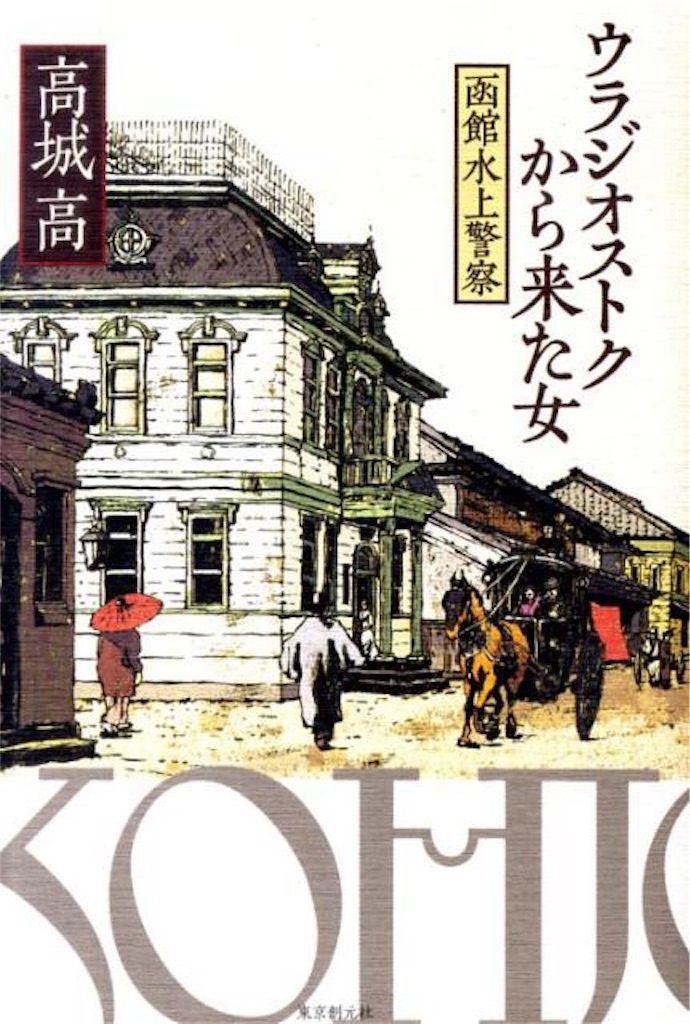
前作。こちらは東京創元社から出ている。

この時代のロシアの決闘と言えば思い出されるのがイリヤ・レーピンのオネーギンとレンスキーの決闘だ。作中で決闘に参加する人物の名前もレーピンなのは、やっぱり作者もこの絵を観たんだろうか。